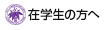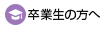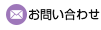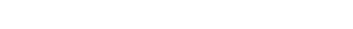12月17日(火)『アドベントチャペルⅣ』
投稿日:2024.12.19
![]()
聖書箇所:『新約聖書、マタイによる福音書2章9-11節』 題:「星の降る夜」
本日の奨励者は、共愛学園前橋国際大学宗教主任の古澤健太郎先生でした。聖書箇所は、”…東方で見た星が先立って進み、ついに幼子がいる場所の上に止まった。…”とあります。東方の博士たちが、輝く星に導かれてイエス様にがお生まれになったベツレヘムの馬小屋にたどり着いたお話しです。
『一般的に、クリスマスらしいと感じる曲を、「クシスマスソング」と呼んだりします。では、この「クリスマスらしさ」をもたらす要因とはいったい何なのでしょうか。クリスマスに歌われる曲として最も多いのは、何といっても「きよしこの夜」でしょう。実はこの歌は、もともとあった賛美歌ではありませんでした。200年ほど昔、クリスマスの直前にオルガンが壊れてしまったオーストリアの教会で、ギターでも演奏できるようにと即興で作られたのだそうです。古くから歌われていた曲ではありませんが、シンプルなメロディで親しみやすく、ギターの演奏でも充分にクリスマスを感じさせてくれます。今では、世界中でクリスマスの賛美歌として愛されています。
1940年制作のディズニー映画に「ピノキオ」があります。その中で使われている曲に「星に願いを」があります。これも、そもそもクリスマスとは全く関係のない曲でした。しかし、スウェーデンやデンマークなど、白夜や黒夜のある北欧の国々で大変好まれました。冬の北欧は、太陽の出る時間は極めて短いです。暗い夜に、一筋の星の光に願いを込めるようなこの歌は、クリスマスに救い主の到来を待ち望む雰囲気にもぴったりだったのでしょう。北欧での大流行は、程なくして米国本土にも逆上陸を果たし、映画と共に世界的に広まっていきました。
この2曲に共通するのは、『暗い夜にようやく届いた一筋の星の光』です。つまり、イエスの誕生日を祝う「クリスマス」を感じさせるものとは、太陽や月のように明るい光ではなく、ようやく届いた弱い光であり、よく見なければ分からない程の、「星の輝き」なのではないでしょうか。クリスマスのこの時季、北半球では一年で最も太陽の出る時間が短い「冬至」にあたります。暗く寂しい冬の夜に、明るい春の到来を待ち望むイメージは、世界の国や地域の差、宗教観の違いなどを越えた、普遍的なものなのかも知れません。2024年は、お正月の大地震や、秋の豪雨災害など、厳しい1年を過ごした地域がありました。世界を見渡せば、長く続く紛争に悩む地域も多くあります。しかし、どれほど暗く辛い夜にも、必ず夜明けがやって来ます。暗いこの世の中にも、必ず一筋の星の光が届くことを信じて生きて行きましょう。』
東方の博士をイエスの産まれた馬小屋へ導いた星のことを『ベツレヘムの星』と呼びます。クリスマスツリーの頂上に星を飾るのは、この『ベツレヘムの星』をシンボル化したものだと言われています。古澤先生は、プレゼンテーションのスライドを使用し、時折ギターを奏でながら、いくつものクリスマスソングを紹介してくださいました。暗い話題の多い昨今ですが、まさに一筋の光を見つけたような、心暖まるチャペルになりました。古澤先生ありがとうございました。
本日は2024年最後のチャペルアワーでした。2025年1月7日は『学生チャペル』です。 メリークリスマス!