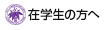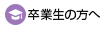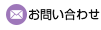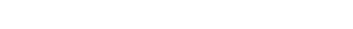2025年4月22日(火)「イースターチャペル」
投稿日:2025.04.23
![]()
聖書箇所:「新約聖書、マルコによる福音書、16章5-7節」
題:【 ガリラヤでイエスに会える 】
本日のイースターチャペルには、日本キリスト教団 前橋教会牧師の 川上盾先生 をお招きしました。イースターは十字架にかけられて亡くなったイエスの、よみがえりを祝う復活のお祭りです。川上先生は、新島短大で初めてキリスト教と出逢った学生にも理解しやすいようにと、有名な映画を例にあげて語ってくださいました。
「そもそもキリスト教は、イエスが死んで3日目に復活し、その事を信じることから始まったと言っても良いでしょう。医学は、人が死ぬのを少しでも遅くしようとするものですが、今の科学技術では、人が死なないようにすることや、死者をよみがえらせることは出来ません。キリスト教の教会牧師である自分も、その事は良く理解しています。では、聖書が語るイエスのよみがえりとはどのようなものだったのでしょうか。人の命が亡くなったら、それで全てが終わってしまうものなのでしょうか。
例えば、遠くに住む知人の消息は、即時に伝わるものではありません。もしも、そうした知人が亡くなったとしても、知らせを聞くまでは、その人の死を意識することはありません。また、お世話になった恩人が亡くなったとしても、その人から受けた恩や大切なアドバイスなどは、自分の心の中で大切に守られ、失われることは無いでしょう。つまり、たとえ生命活動が失われていたとしても、その人とのふれあいや関わり、いただいた恩恵や愛情などは決して失われることはないのです。世の中には、物理的・即物的なものだけではない何かがあるのです。
1930年代の米国映画に[怒りの葡萄]があります。原作はジョン・スタインベックの小説で、当時のアメリカ文学を代表するものです。世界的な大恐慌による経済不安や、干ばつ被害により不作に悩む農民と、資本家との社会的身分差別やその軋轢、そしてそこに立ち向かう人々の不屈の人間像がテーマの名作です。主人公であるトム・ジョードの一家はオークランドの土地や財産を始末して、古いトラックを購入します。それに家財道具を詰め込んで、新天地カリフォルニアを目指します。しかし、行く先々で使用人に搾取されるなど酷い扱いを受け、常に厳しい生活を余儀なくされています。トムは、こうした社会の矛盾に怒り、弱者に寄り添う活動家を志し、家を出る決意をします。トムは慕っていたケイシーの言葉をもちいて、母に自分の思いを語ります。
『ケイシーが言っていた。一人の魂は、大きな魂の一部なんだと。その魂は、万人のものだ。だからおれは、暗闇の中にもいるってことさ。母さんが目を向ければね。飢えた人が騒ぐ時もそこにいる。警官がおれの仲間を殴っている時も。仲間が怒りで叫ぶ時も。腹をすかせた子どもが 食事を見て喜ぶ時も。人が自分で育てた作物を食い、自分で建てた家に住む時も、おれはそこにいる。』
本日の聖書箇所には、マグダラのマリア、ヤコブの母マリアらがイエスの墓に向かう場面が書かれています。しかし、墓にイエスの遺体は無く、そこにいた白い衣の若者(天使か)から『ナザレのイエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれる』・・と示されます。ガリラヤはエルサレムから見れば北方で、どちらかと言えば辺境の地方ですが、そこはイエスが最初に宣教を始めた場所、イエスが小さき人々を大切にされた、その関わりが残る場所なのです。そう考えれば【ガリラヤ】とは、はるか遠くにあるだけの場所ではなく、我々の身近にあるものなのではないでしょうか。」
川上先生は、イースターには必ず映画のこの台詞を思い出し、そのたびにこの聖書箇所をイメージするのだそうです。チャペル奨励の最後には、ご自身の音楽伝道活動「これもさんびか」の中から「ガリラヤで主イエスに会える」を歌ってくださいました。作詞作曲はもちろん川上盾先生、ご本人のギター演奏での なま歌披露!およそ150名が入った新島短大新木造校舎「新島の森」に、イースターを祝う歌声が心地よく響き渡りました。