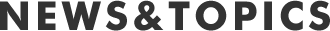【実施報告】10/7(火)「学生チャペル」
報告者:キャリアデザイン学科1年 フードビジネス専攻 横山絢音
キャリアデザイン学科1年 キャリアデザイン専攻 小柴虹乃
聖書箇所:『新約聖書、マタイによる福音書6章19-21節』
本日は夏の集中講義参加者による研修報告です。「ボランティアプロジェクト」は栃木県黒磯市でアジアの農村指導者を養成する専門学校である【学校法人 アジア学院】にて、「ボランティア活動」は高崎市榛名町の【社会福祉法人 新生会】にて実施しました。それぞれ宿泊を伴う体験実習による研修です。新島学園短期大学では、どちらも例年実施している集中講義です。本日の報告者は、どちらも1年生でした。それぞれの実習でご自身の体験を通して、今までは気がつかなかった事に気づき、そこに課題を見出し、その課題の解決に取り組もうとする姿勢が感じ取れます。どちらも大学1年生らしいみずみずしい感性を感じさせる報告となりました。
◆キャリアデザイン学科1年 フードデザイン専攻 横山絢音
私は、アジア学院での2泊3日のボランティアプロジェクトに参加しました。新島学園、共愛学園の高校生とも一緒で、とても内容の濃い3日間でした。そこでの活動で実施したことや印象に残ったことを発表しようと思います。
アジア学院は、日差しは強かったのですが、自然に囲まれていて空気も新鮮な場所でした。学院の皆さんは、大変優しく接してくださり、安心して活動することができました。初日にはキャンパスツアーがありました。ガイドをしてくださった方は、非常に熱心に学院内の事を紹介してくださいました。その後には、トークセッションを行いました。二日目には農業体験を行いました。まず朝早くにラジオ体操をして、その後に草むしりを含めて農作業でした。アジア学院では、なるべく機械を使わないことを大切にしているので、ほぼ手作業で草を刈ったり、野菜の収穫をしたりする作業となりました。そこでは、アジア各地から学びに来ている留学生の方々とコミュニケーションを取り合い、集中して作業に取り組むことが出来ました。とれたての野菜を食べるとみずみずしくて大変おいしかったです。まさに、自然の恵みを感じることが出来ました。
その日の午後は、「平和といのちに関する授業」を行いました。「突然、好きな食べ物が食べられなくなってしまったらどうするか」とか、「自分にとって平和な時と、平和ではない時とはどのように違うのか」などについての話し合いを行いました。グループで互いに考えを深め合う活動となり、とても勉強になりました。また、授業の中にはキャンパス内をめぐる野外での活動もありました。鶏の生みたての卵を手にしたり、豚小屋の中もじっくりと見学することが出来ました。これらの活動からは、生命の尊さを学ぶことが出来ました。そしてその後に、「これから自分たちは、どのように行動をしていくのか」を考え話し合う時間となりました。夕方には宿舎に戻りました。参加者みんなで力を合わせてインディアンカレーを作る実習です。スパイスも自分たちで調合しました。大きなバナナの葉をお皿にして盛りつけました。スプーンなどを使わずに、素手でカレーを食べました。一緒に参加した新島学園や共愛学園の高校生のみなさんと共に交流を深めることが出来、大変貴重な体験になりました。
アジア学院での学びは、班で話し合い考えを深めていくプロジェクトが多かったと思います。他の人の意見を聞くことは新たな発見につながり、いままでの知識を広げ、さらに深めることが出来るようになったと感じています。アジア学院に着いたばかりの頃は、なんだか恥ずかしくて、他の人たちとコミュニケーションをとるのにも気が引けていました。でも、しばらくすると交流ができるようになりました。そして、その深まりとともに楽しさがどんどん増えていきました。自分の思いや考えを直に言葉で伝えることは、本当に重要だと改めて気がつきました。ボランティアプロジェクトでアジア学院を訪れていた時季は暑い日が多く、体力的にきついところもありました。しかし、命の大切さやコミュニケーションの大切さを学べる大変有意義な研修になりました。ご清聴ありがとうございました。
◆キャリアデザイン学科1年 キャリアデザイン専攻 小柴虹乃
私は、社会福祉法人新生会が運営する高齢者施設で、3泊4日のボランティア研修に参加しました。この施設は健康型の方から要支援・要介護の方、特別養護老人ホームの利用者さん、さらには、終末期の看取りまでを一貫して提供しています。そして、「入居者一人ひとりの生活や人生に寄り添うこと」をその理念としています。新生会では「あなたが去ることを希望されないかぎり、最後までお世話させていただきます」という言葉を創設以来大切にされています。この言葉からは、利用者への深い思いや敬意が今も生き続けていることを強く感じました。私自身、この言葉を知った瞬間から、ボランティアとしての責任の重さと、利用者さんと向き合う姿勢の大切さを意識するようになりました。
施設では、日常生活のサポートとして食事の配膳や居室の清掃を行うほか、折り紙や会話を通じたコミュニケーション活動もしました。ある日の折り紙の時間のことです、一人のおばあさんが「昔はうまく折れたのに・・・」と微笑みながら丁寧に紙を折る姿がとても印象的でした。その手は少し震えていましたが、集中して折り続ける姿からは「年齢を重ねても楽しむ心を大切にしている」という強い思いが伝わってきました。また、折り紙を折る手を見守りながら一緒に完成品を喜ぶ時間は、ただの作業ではなく互いの存在を認め合う時間であることを肌で感じました。そのほかにも、施設で過ごす中で利用者さん皆さんの一つひとつの行動や表情から学ぶことも多くありました。たとえば、食事の際にすこしずつ慎重に口に運ぶ様子や、日々の小さな工夫を楽しむ方の姿を見て、日常生活の中で自分では当たり前だと思っていた行動も、実はそうではないことがある事や、時間はかかっても待つことの大切さにあらためて気づかされました。とりわけ、笑顔で話しかけてくださる方々の柔らかな表情や感謝の言葉は、私の心に深く残り「支えることの喜び」とは何かを考える大きな契機となりました。それに加えて介護職の方々の仕事は厳しいけれども、やりがいも大きいことを間近で感じる事が出来ました。
介護職の方々は、入居者さんの体調や気持ちの変化に細かく気を配り、時には急な怪我や病気の対応をすることもあると伺いました。それでも、どの職員の方も笑顔を絶やさず、利用者さんの安心や笑顔のために全力を尽くしている姿が印象的でした。ある職員の方は「大変なことも多いけれど、利用者さんが笑顔になってくれた時や『ありがとう』と言われた瞬間に、この仕事を選んでよかったと心から思える」と話してくださいました。その言葉を聞き、介護は肉体的な労力や精神的な負担を感じるだけではないのだ、人の人生に寄り添い、支え合うことにより仕事へのやりがいが生まれや、その尊さを実感することが出来るのだと感じました。
このボランティア体験を通じて私は、介護とは単なる業務ではなく、人の人生に寄り添う責任であり、覚悟を伴う仕事であることを学びました。「最後までお世話させていただく」という誓いが、ただの言葉ではなく現場で実践されている現実に触れることで、その重みと尊さを強く感じました。そして、高齢者の方々の笑顔や丁寧な生き方に接することで、私自身の人生観や「生きるとは何か」という問いに向き合う時間にもなりました。普段の生活では気づきにくい、人と人とのつながりや、人を尊重することの大切さ、そして人生の一瞬一瞬の価値を実感することが出来ました。
新生会でのボランティア活動は、私にとって福祉の深さと人の尊厳を問い直す、かけがえのない体験となりました。これまでに築き守られてきた理念と、現場で生き続ける「最後までお世話させていただく」という言葉は、直に利用者さんと関りを持った私の心に非常に強く響きました。この経験を胸に、今後の自分自身の生き方においても、誰かに寄り添い、尊重し、支え合える人間でありたいという思いを以前にも増して強く抱くようになりました。
新生会での体験は、想像していたよりもずっとあたたかく、心に残る時間となりました。利用者の方々とお話をしたり一緒に活動をしていくと、自然と笑顔になれる瞬間がたくさんありました。最初は緊張するかもしれませんが、ほんの少し勇気を出して話しかけてみると、相手の優しさやあたたかさに触れられると思います。活動をしていく中で、「支えること」や「寄り添うこと」の意味を考えたり、人と人とのつながりの大切さを感じることがきっと出来ます。無理をせずに自分のペースを守って素直な気持ちで関わることが何より大切なことだと思います。来年もこの集中講義「ボランティア活動」が実施されると思います。参加される方は是非、新生会でしか味わうことのできない学びや出会いを大切にしてみてください。ご清聴ありがとうございました。