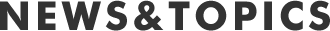【実施報告】9/30(火)「始業チャペル」
奨励者:髙山 有紀 先生(新島学園短期大学 学長)
聖書箇所:「新約聖書、ヨハネによる福音書4章35-37節」 題:【 「日本文化」に見る 秋 について 】
本学学長の高山有紀先生は、今回、【 「日本文化」に見る 秋 について 】と題して奨励をしてくださいました。ご専門である日本文化を踏まえてのお話です。寄り添うような優しい口調でありながらも、格調高い奨励になりました。
【 秋学期が始まり、皆さんの声が学園に戻ってきました。皆さんの存在は学校に活気を与えてくれます。こうして秋学期を迎えられたことを感謝します。朝晩快適な気温になり、最近ようやく吹く風が涼しくなり、確実に「秋」の気配を感じます。今年の夏は本当に暑かったですね。秋の訪れが本当に嬉しく、ホッとしたことでした。今日は「秋」という季節のイメージや、日本文化との関連性について考えてみたいと思います。
まず「秋」という漢字に注目してみましょう。調べてみると、これは、日本で生まれた漢字を意味する、国字(こくじ)ではなく、中国から伝来した漢字が略字となったものであることがわかりました。略字は収穫を意味する「のぎへん」に「火」と書きますが、旧字では「穐」(のぎへんに亀)です。古代には、亀の甲羅を火であぶって、その割れ方で農作物の豊作を願う占いなどもあったのです。そのため、文字の偏(へん)や旁(つくり)から、収穫や儀式、占いなどを意味する語であることが確認されます。秋は確かに実りの季節です、収穫への感謝は地域や文化の違いを超えたものだと考えられます。自然への感謝、命が守られていることへの感謝。日本においてもそうした自然や命の営みが、秋のイメージと切り離せないものとなっています。
秋のイメージのひとつに「芸術の秋」があります。そこで江戸時代の絵画、なかでも庶民に人気だった「浮世絵」を取り上げてみたいと思います。浮世絵には、「秋の月」を取り入れた作品がとても多いと言われています。お月見を楽しむ人々を描いた絵、秋の夜長を楽しむ家族団らんの光景、そしてその背景にさりげなく描き込まれた「月」。江戸時代の人々に大人気だった歌舞伎を見た帰り道の人々を照らす「月」。そうした浮世絵は、海外の印象派の画家たちに強い影響を与えたといわれています。月にうっすらとかかる雲や、月の光を受けて人々の足下にうっすらと描かれる影は、その技法としてはとても難しいものなのだそうです。月が描かれた浮世絵、当時の人々は好んでそうした絵を購入し、明るい月の光に照らされる日常生活を大いに楽しんでいたのでしょう。それと同じく 「お月見」を楽しむ習慣も江戸時代に登場しました。江戸では高輪や芝浦など海辺の地域で月が出るのを待ち、楽しみながら食事をし、お酒をたしなむ習慣があったようです。先ほど収穫の話をしましたが、お月見は、ススキやお団子などのお供えをすることから想像できるように、収穫を祝う収穫祭の側面があります。そのほかにも、秋祭りはまさにみんなで収穫をお祝いする行事でしょう。
さて、この夏休みの間、皆さんはいろいろなことを頑張ってこられたと思います。進路を決める試験を受けた人、ボランティアやインターンシップで新しい体験にチャレンジした人・・そうした皆さんの体験は言うまでもなく「収穫物」です。(最近流行の教育用語では「成果物」とも言うようです)この秋学期には、ご自身で頑張ったことや、新しく体験したことをぜひ人に語る体験をしてみてください。・・次週10/7のチャペルアワーでは、集中講義の「ボランティアプロジェクト」や「ボランティア活動」の体験報告が予定されています。そうした学生奨励のような語り方であっても良いでしょう、話すことが難しければ自分で記録するだけでも良いと思います。ご自身の経験を客観視してみる活動は学生時代にとても大事なことだと思います。
CC学科CD学科の両学科とも2年生はこれから実習や、ゼミでの論文作成など2年間の集大成に向かっていかなければなりません。1年生は2年生への進級に、そして進路決定に向けての準備態勢に入っていきます。秋のおいしい収穫物をたくさんいただいて、夏の暑さで受けたダメージを補給しましょう。皆さんそれぞれが手にした収穫物を携えて、張り切って秋学期をスタートさせていきましょう。
ところで、学生の皆さんにだけ「頑張れ」というのは不公平ですよね。新米学長は、以下のような行事を始めることを宣言します。『秋学期には、みなさんの声を聴く「 ランチ会 ・ ランチミーティング 」を開催します!』月に1回程度を考えています。お弁当などを持って集まってもらうのはどうでしょう。学生生活のことや、授業についてのこと、学園の設備のことなど・・みなさんの要望を伺ったりしたいと考えています。みなさんが新島学園短期大学での学生生活を思い切り楽しめる環境を作れるよう、いろいろな話し合いを通して直接ご意見を聴取したいと思っています。掲示やポータルで呼びかけますから、ぜひ参加してください。よろしくお願いします。】
「秋」という文字の成り立ちからは、農作物の「実りの秋」を解説してくださいました。「浮世絵」に描かれた月の光や影など秋の風物を通して「芸術の秋」を解説してくださいました。そしてその「秋」という語が醸し出すイメージから、学生の経験や成長を「収穫」や「成果」としてとらえて語ってくださいました。髙山学長の視点は、学生一人ひとりに向けられ、個々の学びのプロセスを暖かく見据えているのです。新短で学ぶ学生への何よりの励ましとなったと思います。「 ランチ会 ・ ランチミーティング 」楽しみですね。髙山先生、素敵な奨励をありがとうございました。