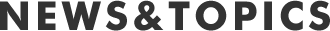【実施報告】9/16(火)「特別チャペル」
奨励者:越後屋 朗 先生(同志社大学 神学部 教授)
聖書箇所:『旧約聖書、詩編31編2節・新約聖書、ローマの信徒への手紙1章17節』
以前、旧約聖書にある詩編を読んだとき、興味深い発見がありました。1987年に日本聖書協会から発行された『新共同訳聖書』では、詩編31編2節の最後が「(あなたの)恵みの御業によってわたしをお助けください」となっていますが、同じ協会から2018年に出された『聖書協会共同訳聖書』では「あなたの正義によって私を救い出してください」となっているのです。「お助けください」と「救い出してください」はほぼ同じ意味ですが、「恵の御業」と「正義」は違います。原典では「ツェダーカー」というヘブライ語の名詞が使われており、基本的な語句の意味は「義、正義、正しさ」です。他の日本語訳聖書にも当たりましたが、『新共同訳聖書』だけが「恵みの御業」となっており、他の聖書では「義」あるいは「正義」でした。
なぜ、『新共同訳聖書』での詩編の翻訳者は「恵みの御業」としたのでしょうか。調べてみると、詩編31編2節(とほぼ同じ表現が出てくる71編2節)はキリスト教、特にプロテスタントにとってたいへん重要な箇所であることがわかりました。ローマ・カトリック教会から分離し、プロテスタントを生み出すことになる宗教改革の中心人物はマルティン・ルターです。その彼に最も大きな影響を与えたと言われる聖書箇所が詩編31:2(71:2)であり、この箇所の解釈こそが宗教改革の出発点だったのです。
中世において、「神の(正)義」は罪や罰と密接に結びついていると一般に理解されていました。つまり、義の神は、人にも義(ただ)しく生きることを求めているはずであり、人は義(ただ)しく生き、罪を犯さず、「能動的」に善行に励まなければなりません。しかし「神の義」は、人が到底到達できないほどの基準であり、その基準の前では、人間は誰しも罪人であり、罰せられるしかありません。人は罪人として生涯を終えることになるのです。それゆえ、義の神は「裁きの神」ということになります。
中世の人々は、義の神によって罪人に与えられる罰を恐れて生き、ルターも同様でした。修道士となったルターは、義の神に自分を「義(ただ)しい」と受け入れてもらうために、自らを厳しく律し誰よりも努力しましたが、どうやっても神は自分を「義(ただ)しい」と受け入れてくれたという確信を得られませんでした。そして、そうした思いのまま、彼は神学博士となり、ヴィッテンベルク大学聖書教授に就任し、詩編の講義を始めることになります。
「神の義」を、罪、罰、裁き、との関連で捉えていたルターにとって、詩編31:2における「神の義」と「救い」との結びつきは矛盾と思われ、どうしても理解できませんでした。彼は必死になって考え続け、講義が71編(2節は31:2とほぼ同じ表現)に進んだとき、「神の義」についてのまったく新しい認識へと至るのです。31:2と71:2ではイエス・キリストのことが言い表されているのであって、「神の義」は罪人を罰する神の権威ではなく、神からの「恵み」そのものであり、それはイエス・キリストという「贈り物」として人間に与えられるものであると。パウロはすでに「ローマの信徒への手紙の1:17で「神の義が、福音の内に、真実により信仰へと啓示されている」と語っています。ルターにおいて、「神の義」と「救い」がキリストを通して一つに結び付いたのです。
ルターの「神の義」理解は次のように説明できます。義の神は、人が完全でなく罪人であることを知っています。だからこそ、愛おしみ、自ら持っている義を人に無償で与えます。それがイエス・キリストの福音であり、まさに神の恵みです。それゆえ人は、神が与える義を「受動的」に受けとめればよいのであり、この受け入れるということが信仰なのです。つまり、人は完全でなく罪人であっても赦され救われるのです。神は「救いの神」なのです。
「神の義」は、神からの(一方的な)恵みであり、救いであり、教会が発行する贖宥状(しょくゆうじょう)①にはまったく意味がありません。だからこそ、ルターは贖宥状を批判する「九十五箇条の提題」を発表したのです。これが宗教改革という大きなうねりを引き起こすことになるのです。あくまで推測に過ぎませんが、『新共同訳聖書』の詩編31:2と71:2において「ツェダーカー」を「義」や「正義」ではなく、わざわざ「恵みの御業」とした翻訳者は、そこにルターの「神の義」の理解を込めたのかもしれません。
注:①贖宥状(しょくゆうじょう)
ローマ-カトリック教会が,罪の償いが免除されるとして発行した証書。
一五世紀末には教会の財政をまかなうため大量に発行され,ルターの批判を呼び宗教改革のきっかけとなった。免罪符とも。