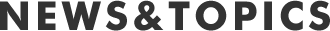【実施報告】9/9(火)「チャペル・アワー」
奨励者:臂 奈津恵 先生(新島学園短期大学 宗教主任)
聖書:『旧約聖書、イザヤ書 2章 2-5節』
本日は夏休みを挟んで久しぶりのチャペルです。本学の宗教主任である臂奈津恵先生の第一声は、「皆さんは夏休みに何をなさいましたか?」でした。ご存じの通り臂先生は、3人のお子さんを育てるお母さんでもあります。臂先生のご家族は毎年夏休みには、何らかのテーマを持ってイベントに臨んでいるのだそうです。今年2025年は、第2次世界大戦が終わり80年となる年です。「戦没画学生」と「従軍画家」の2つをテーマとして美術鑑賞に行ったのだそうです。
【戦没画学生慰霊美術館 無言館】
無言館は長野県上田市にあります。戦争当時に美術学校に通っていた学生で、徴兵され戦地で亡くなった方々の作品が展示されています。その中には未完成のものもあり、より一層その無念な心の内が感じられます。館長の窪島誠一郎さんは著作家、美術評論家として知られています。ここの美術館を建てる時には、出征経験のある画家、野見山暁治さんと共に戦没者遺族を一軒一軒たずね歩いて展示させてくれるようお願いしたと言われています。そうした戦没者作品の募集は現在も続いています。
臂先生家族が訪れたのは夏休み中であったため、見学者は多かったそうです。それでも美術館周辺は静寂に包まれていました。園内の一角には、沖縄県の摩文仁の丘から運んだ石を敷き詰めた箇所があります。沖縄は太平洋戦争で最も激しい市街戦の現場です、今でも遺骨が見つかることは珍しいことではありません。お子さんたちも神妙な面持ちで見学されていた事でしょう。
【軽井沢安東美術館 (日本で唯一の藤田嗣治の作品のみを展示する美術館)】
この美術館は、代表理事である実業家の安東泰志さんが、私財を投入して設立しました。ここは臂先生と美術好きの長女さんとの二人だけが入館し、じっくりと鑑賞したのだそうです。
藤田嗣治が描くものは本来、「少女」や「猫」などの可愛らしいものが中心でした。しかし戦時下において、陸軍美術協会理事長に就任することとなり、従軍画家として国威高揚を示す作品を意欲的に創作しました。しかし、終戦後は従軍画家であったことを理由に、画家仲間や世間からも攻撃の対象となってしまったのです。そのため藤田は日本を離れることを決意し、長く留学生活をしていたパリへ渡り、カトリック教会で洗礼を受け「レオナール」という洗礼名が付けられました。パリで多くの芸術家たちと交わる中で、フランスに帰化し[レオナール・フジタ]として生きることになったのです。そして晩年のフジタの作品には「聖母子」や「キリスト降架」などクリスチャンらしいモチーフが数多くみられます。
臂先生による奨励は【「その筆で何を描くか」】と題されたものでした。生きて帰り、もっと絵を描きたかっただろう悔しさや、画家としての素晴らしい才能により描かれた作品が戦後激しい批判を浴びるなど、画家達には様々な悩みがあったと思われます。本日の聖書箇所には「・・・その剣を鋤にその槍を鎌に打ち直す。国は国に向かって剣を上げずもはや戦いを学ぶことはない。・・・」とあります。このフレーズはニューヨークの国連本部前の『イザヤの壁』に刻まれていることでも知られています。臂先生は最後に、「同じ金属でもその使い方によって武器にもなれば、農具にもなります。武器を手に取らなくても私たちの言葉が人を傷つけることがあります。この世界から、争いやいさかいが無くなるようにと祈りながら家族旅行を終えました。」と語りました。
戦争に関係するお話はその性格上どうしても暗くなりがちです。しかし、話題にして語り継いでいかなければならない内容のものでした。臂先生の奨励はスライド写真やイラストなどを例示し、具体的にわかりやすく解説してくださいます。本日も視覚的にもとらえやすく、理解しやすいお話になりました。今日は9月9日、新学期は始まったばかりです。流れが出来つつも、夏の疲れが出てくる頃です。聴く人すべての心に寄り添ってくれるような優しいお話しでした。臂先生ありがとうございました。